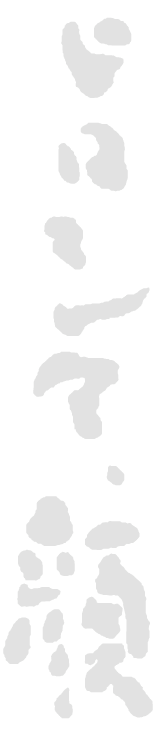金には癒やしと希望を感じさせる力がある。
そこには愛と平和がある。
それはすなわち、
ヒロシマが求め続ける世界恒久平和に通じる。

金には癒やしと希望を感じさせる力がある。
そこには愛と平和がある。
それはすなわち、
ヒロシマが求め続ける世界恒久平和に通じる。

疎開していた五日市から三篠に立ち寄った8月14日、
広島は見渡す限りの焼け野原で異臭が漂い、
全焼した自宅と工場の跡には煙突が1本焼け残っていました。
これからどうなるんだろう―。
当時は国民学校5年生で、不安でいっぱいでした。
翌春、身を寄せていた知人宅から広島に戻ると、
まだ瓦礫が広がるまちに、煙突が悠然と立っている。
「しっかり、やるべきことをやれよ!」
そう言われた感じがしました。
私の覚悟の原点です。
かつて辺りの人々がよりどころにした煙突は、
いまも使われています。
焼け落ちた工場の跡地に残った煙突
1945(昭和20)年10月 米国戦略爆撃調査団撮影/米国国立公文書館提供

疎開していた五日市から三篠に
立ち寄った8月14日、
広島は見渡す限りの焼け野原で異臭が漂い、
全焼した自宅と工場の跡には煙突が1本焼け
残っていました。
これからどうなるんだろう―。
当時は国民学校5年生で、不安でいっぱい
でした。
翌春、身を寄せていた
知人宅から広島に戻ると、
まだ瓦礫が広がるまちに、煙突が悠然と
立っている。
「しっかり、やるべきことをやれよ!」
そう言われた感じがしました。
私の覚悟の原点です。
かつて辺りの人々がよりどころにした煙突は、
いまも使われています。
焼け落ちた工場の跡地に残った煙突
1945(昭和20)年10月 米国戦略爆撃調査団撮影/米国国立公文書館提供

▲工場に立つ久永洪さん。金紙の光が室内を100年企業の作業場を明るくする
-
Profile
Hiroshi Hisanaga
久永 洪
1934(昭和9)年10月27日、広島市三篠本町(現・広島市西区三篠町)生まれ。生家は1905(明治38)年に「久永清次郎商店」として創業した金銀の襖・壁紙製造「歴清社」。両親、祖母、11歳上の兄、3歳上の姉の6人家族で、父の弟と母の妹が結婚した家族5人、従業員の男性と同居していた。尋常小学校が国民学校になった1941(昭和16)年春、大芝国民学校(現・広島市立大芝小学校)に入学。戦時統制が強まる中、家業の金紙製造は1943(昭和18)年に中断し、広島陸軍被服支廠に納入する包装紙の製造に切り替える。
国民学校5年生だった1945(昭和20)年7月、母の郷里である五日市(現・広島市佐伯区)に、母の妹とその子ども3人と一緒に疎開する。8月6日の朝は五日市国民学校の校庭で朝礼を終えて、児童が隊列を組んで教室に向かっていた。東の空にピカーッと鋭い閃光が走り、爆心地から10キロ離れた場所にも地響きのする轟音が響いた。
三篠の自宅と工場は爆心地から2.2キロ。コンクリート造の煙突と危険物を収めていた倉庫を残して倒壊・全焼した。父・清次郎さんは重傷を負うも母・アサノさんに助け出されたが、祖母・シゲさんは避難途中にショック死したという。兄・清八さんは出征しており、女学生だった姉・佐智子さんは東練兵場での動員作業中に被爆したが無事だった。
疎開先では広島の惨状を伝え聞くばかりで不安は募る一方だったが、11日に両親と姉が祖母の遺骨を持って五日市にたどり着き、再会を果たした。終戦前日の14日、飯室(現・広島市安佐北区)の知人宅へ避難していく道すがら、焦土と化した広島を目の当たりにし、工場と自宅の跡に焼け残っていた煙突と倉庫を見た。
1946(昭和21)年春、飯室から三篠に帰ってくる。家業を再建するため一足早く戻っていた両親、復員してきた兄らとともに、食糧難と戦後の混乱を生き抜く。屋根の防水シートや木造船塗料の製造などでしのぎながら、父は本業である金紙製造の再開をうかがっていた。新制中学の1期生として入学し、高校卒業後に広島大学工学部工業化学科に進むも、後に工業経営学科に転科。大学生活も終わりに近づいた頃、金紙製造を復活させていた家業を手伝ううちに、生家が代々紡いできた技術の卓越さを知った。
社長の座を継いだ兄を技術担当者として支えながら、国内外に販路を広げた歴清社がオンリーワンの技術を誇る企業として発展していくのに貢献した。1981(昭和56)年末に兄が急逝し、後継として4代目社長に就任した。創業100年の2005(平成17)年に退き、2024(令和6)年10月まで相談役を務めた。
歴清社が継承してきたものは技術だけではない。あの日の記憶―焼け残った煙突と倉庫は現役で、戦後に建てた現在の工場は被爆した小学校の廃材を移築して造られた。そこに刻まれているのは、懸命に生き抜いた家族の歴史と、広島の戦後復興と発展。ヒロシマの大切な財産を守り続けている。
◀︎工場に立つ久永洪さん。金紙の光が室内を100年企業の作業場を明るくする
幼少期の思い出
物心ついた頃には日本は戦争への道を加速させていた。
祖父・初代清次郎が興した工場は既に三篠に移っており、一家総出で家業の金紙作りに励む中で育った。
現在は住宅や中小の工場がひしめく横川から三篠、大芝にかけての一帯は、昭和の初期には工業が盛んな地域として発展していた。太田川の上流から流してきた材木をためる貯木場があった。いまも広島を代表する企業である西川ゴム工業、ミカサ、モルテンが創業した地でもあり、それに付随して修理やメンテナンスを手がける鉄工所も集まっていた。
その周囲は畑が広がり、キュウリやトマトを栽培し、蓮田も多かった。朝早くから農家の人たちが肥料にする人糞を集めに回ってきていた。戦後に太田川放水路になった川はまだ、幅の細い小川だった。
工場と一緒だった自宅には大家族が暮らしていた。父の2代目清次郎、母のアサノ、祖母のシゲ、11歳上の兄・清八、3歳上の姉・佐智子。さらに父の弟・繁雄は母の妹・末子と結婚し、いとこに当たる子ども2人がいた(終戦の年に第3子が生まれる)。従業員の定森定一も住み込みで働いていた。夜には出入りの職人らも交えて、一升瓶を並べて酒を酌み交わしながら、あれやこれやと話をしながら情報交換するのが常だった。
幼稚園に行くわけでもなく、近所の寺で毎週日曜日に開かれる寺子屋に通い、お坊さんの説教を聞いた。母は朝暗いうちから、工場で使う糊を五右衛門風呂の3倍くらいはあった大きな釜で炊いていた。母は金紙に魅了されて、親が薦める縁談を断って父と結婚した。祖母が子どもの世話係で、参観日でもないのに毎日学校に顔を出した。
両親たちが汗を流す工場が、子どもたちの遊び場だった。統制経済が強まる中、贅沢品のおもちゃを買ってもらえるような時代ではない。珍しい機械や工具があり、迷路のように広い工場は、かくれんぼに最適で、近所の子どもたちもよく出入りした。ちょろちょろしていて従業員から「おまえら、いけんぞ」と何度も怒られた。機械いじりが好きな父は何でも自作しようとするので、大工や職人も多くやってきた。はなたれ小僧が大工さんに向かって「いがんどる(歪んでいる)でえ」と小生意気なことも言った。
総力戦体制が強化され、尋常小学校が国民学校に改称された1941(昭和16)年、大芝国民学校に入学した。その年の12月、日本とアメリカの戦争が始まる。低学年の頃は給食があり、3年生くらいまでは普通に授業もしていた。父から「のらくろ」「冒険ダン吉」の漫画本を買ってもらったのを覚えている。4年生の頃には空襲警報の発令で帰宅を命じられることが増え、教室の板をはがして床下に防空壕をつくり、運動場は開墾してカボチャやイモを植えた。だから運動会もできなかった。
土の悪い菜園で採れたカボチャはとても堅かった。食べ物が配給制になり、だんだんと貧相になっていくのが子どもにも分かった。白米を食べる機会がなくなり、麦飯になり、それが雑炊になり、具のサツマイモもイモの部分ではなく茎になり。高粱(コーリャン)は腹に合わず下痢をした。
この戦争はよくない―。子どもながらに思ったが、口には出せなかった。なにしろ、日本は戦争に負けた経験がなく、敗戦がどういうことなのか想像できなかった。軍隊のようなスパルタ教育の教師がいて、全員が問題を正答しないと次に進まないし帰れない。星を見ながら下校したこともあった。
家業の工場経営も苦しくなった。嗜好品の金紙は需要がなくなり、従業員も出征していく。1943(昭和18)年、18歳になっていた兄が陸軍に召集された。父は陸軍被服支廠から工場の完成品をくるむ包装紙を作る仕事を取ってきた。そのための機械も自前で作った。薄いロール紙をコンニャク糊で5枚貼り合わせると、ベニヤ板のように強く耐水性もある包装紙になった。貼り合わせのコンニャク糊を蒸気で乾かすための煙突は鉄筋コンクリート造の頑丈な円形に仕立てた。高さは20メートル以上あり、周囲からも目立った。小学校を出ただけで、専門に技術を学んだわけではない父は夜通し設備づくりに励み、工場の床に敷いたむしろの上で朝を迎えたこともしばしばだった。
1945(昭和20)年になると本土決戦が叫ばれるようになる。自宅工場の地下には近所の人も入れる大きな防空壕が掘られ、さらに近くに持っていた500坪ほどの土地にも倉庫と防空壕を作って工場の物品などを疎開させた。まちなかでは空襲に備えて家屋を取り壊して防火帯をつくる「建物疎開」が急ピッチで進められ、国民学校の児童は集団疎開や縁故疎開を強いられる。母の郷里・五日市に疎開したのは原爆投下の前月だった。

1943(昭和18)年撮影。祖母シゲを中心に同居の2家族。右側6人が長男清次郎の家族
(前列右から妻のアサノ、姉の佐智子、久永洪さん、祖母のシゲ。後列右から父の清次郎、兄の清八)
左側4人が次男・繁雄の家族(前列右から平治と益子、後列右から繁雄と妻の末子)
1943(昭和18)年撮影。祖母シゲを中心に同居の2家族。右側6人が長男清次郎の家族
(前列右から妻のアサノ、姉の佐智子、久永洪さん、祖母のシゲ。後列右から父の清次郎、兄の清八)
左側4人が次男・繁雄の家族(前列右から平治と益子、後列右から繁雄と妻の末子)
8月6日
軍港のある呉が空襲で焼かれ、次は広島じゃないのか。その恐れから疎開した母の実家は、五日市の光禅寺という古刹の門前にあった。広島市の中心部から西に約10キロ。母の妹・末子(父の弟・繁雄の妻)とその子ども3人と5人で移った。仕事のある両親は三篠に残り、親子離ればなれの暮らしになった。当時の五日市はまだ田畑が多い地域だったが、食べる物が豊富だったわけではない。疎開してきた家族を受け入れたのだから、なおさらだった。その頃、兄の清八は陸軍で食糧の補給を担当する任で岡山におり、姉の佐智子は県立広島第二高等女学校に通っていた。
五日市は海に近く、広島湾の先にある呉が空襲される炎が見えた。米軍機のグラマンが海沿いを旋回しながら飛んでいく。こりゃ、どうにもならんでえ。子どもにも分かった。
8月6日は月曜日で、校庭での朝礼を終えて隊列になって教室に向かっていた。東にある小高い山の向こうでピカッと光った。青空を雲がものすごい勢いで横筋状になって流れてくる。ドガーンという爆音と地響きがとどろき、先生は「伏せえ」と叫んだ。とっさに目と耳を手でふさいで、うつぶせになった。恐る恐る目を開けると、木造校舎の2階から割れた窓ガラスが落ちていて、けがをした児童がいた。教室に入ったらほこりだらけ。何が起きたのか全く分からず、先生を待つ間に話をする者はいない。先生は「広島に大きな爆弾が落ちたらしい。掃除を済ませて家に帰りなさい」と告げた。
家に帰って午前10時ごろだっただろうか、空が急に暗くなって大粒の黒い雨が降ってきて中庭を濡らしたのを覚えている。何か異様なことが起きている。それしか分からなかった。
しばらくすると家の裏口に「水をください」と訪ねて来た人があった。知らない女性で、頭髪はボウボウに乱れ、顔はほこりで薄黒く幽霊のよう。腕の表皮が火傷ではがれてぶらぶらとしていた。車にでも乗せてもらって五日市までたどりついたのだろうか。しばらくいて、どこかに去っていった。
家中の誰も口を開かない。それは想像を絶する恐怖だった。大人だって連絡を取る先がなかったのだ。あれほど空腹に悩まされていたのに、昼になっても食欲は全くなく、お茶を飲んで過ごすばかりだった。三篠の両親は、姉は、繁雄おじさんは大丈夫なのか?その日は夜になってもなかなか寝付けなかった。
翌日になっても広島の状況は伝わってこない。学校も休校だった。どうなるんかいのう。大人たちがぼそぼそとしゃべる声が聞こえる。部屋をごそごそしているばかりだった。2日たった8月8日、母の兄と末子は居ても立ってもいられないとばかりに、2人で広島に向かった。己斐駅(現・西広島駅)まで汽車に乗り、焼け野原を目の当たりにして覚悟したという。炎天下を歩いてたどり着いた三篠で見たのは、煙突と倉庫など一部を残して丸焼けになっていた自宅と工場だった。家族や従業員の行方は分からず、悄然として夕方、五日市に引き上げてきた。帰りを待っている間も、遊ぶ気にもなれなかった。

工場の煙突は原爆の爆風と猛火に耐えて残り、今も使われている。
ヒロシマの惨禍と復興の証人でもある

工場の煙突は原爆の爆風と猛火に耐えて残り、今も使われている。
ヒロシマの惨禍と復興の証人でもある
両親との再会

祖母シゲと父清次郎
父と母は生きていた。学徒動員の作業で広島駅の北にある東練兵場にいた姉も助かった。それが分かったのは3日後の8月9日だった。
その日も末子たちは手がかりを探しに広島に出向いた。叔父の繁雄は建物疎開の作業で広島市役所に近い雑魚場町にいたはずだった。そこは焼死体が折り重なり、繁雄を見つけることはできなかった。帰る途中で三篠に立ち寄ってみると、姉・佐智子の伝言が板切れに焼け墨で書いてあった。従業員の森本良一と長束にいるとあった。同じ日、従業員の1人が山を越えて五日市にやってきて、両親が生きていることを伝えてくれた。
あの日、自宅と工場では何があったのか。後に聞いた話はこうだ。朝から父・清次郎は工場の3階で陸軍被服支廠に届ける試作品の包装紙を準備していた。突然の閃光と轟音。工場の土壁は崩れ去り、ガラスの破片が左上腕をえぐった。「逃げろ!」と従業員たちに向かって叫ぶも出血がひどく、意識が遠のいていく。何とか自宅の台所にたどりつくと、血まみれの息子を見た祖母・シゲはへなへなと座り込んでしまった。母・アサノは瀕死の父を抱きかかえ、従業員の定森定一にシゲを連れて逃げるようお願いする。
「わしゃ、もうええ。この工場と運命をともにする」。そう言う父を無理やり敷布団に乗せて引きずり、非常持ち出し用の鞄を肩にかけて大芝国民学校へ。学校で借りた担架に父を乗せて、避難する人たちでひしめく街道を北に向かった。古市(現・広島市安佐南区)で応急手当を受け、さらに父を馬車に乗せてもらい、母は歩いて可部(現・広島市安佐北区)へ別々に逃れた。午後8時ごろに可部に着いた母は、救護所になっていた寺を回って父を捜し、3カ所目の勝円寺でようやく見つけた。
父は目を閉じて動かなかったが、手を握ると息をゆっくりと吐くのが分かった。祖母は大八車で運ばれる最中に亡くなっていた。重傷を負った息子を見たショック死だったのだろうか。
8月11日午後、みすぼらしい姿の両親と姉、従業員の定森が五日市にやって来た。何も言えなかったが、うれしくて泣いた。風呂に入って落ち着いてもらった。祖母は既に焼かれて遺骨になっていた。
父はいざというときのために飯室(現・広島市安佐北区)の知人・佐々木家にやっかいになることをお願いしていた。いつまでも五日市にいられない。8月14日朝、飯室へ向けて出発した。五日市から己斐までは汽車で、その先は歩いて三篠へ。そこで初めて焼け野原になった市内を見渡した。南には似島が、東には広島駅が見えた。ところどころに散在する遺体にウジ虫がわき、異臭を放っていた。三篠まで来ると煙突1本と危険物を入れていた倉庫を残して全てが焼けていた。いったいどうなるのか。不安しかなかった。
ひたすら北に向かって歩き、途中でトラックに乗せてもらい、午後7時ごろ可部に着いた。こんなときでも父は、祖母の初盆であることを忘れなかった。小さな仏壇と仏具を買い求めた。緊急時に備えて腹巻きには札束を収めていた。飯室に着いたのは午後9時ごろ。佐々木家があるのは、わずか9軒の集落。谷底を流れる小川に蛍がたくさん見えた。真昼には地獄絵図のような焦土を抜け、夜には幻想的な光の舞い。暗闇に死者を鎮魂するかのように思えた。

飯室に向かう途中で買い求めた仏壇は今、久永洪さんの自宅にある。金箔は洪さんが自ら貼った
生活を立て直す
8月15日午後に何か重大な発表があるらしい。ラジオを持っていた飯室の佐々木家には集落の大人たちが集まっていた。山深い地では音声は聞き取りにくい。初めて聞く天皇陛下の声。みながシーンと黙り込んでいた。日本は戦争に負けたのだ。
飯室での暮らしはしばらく続いた。空腹に悩まされていた子どもにとって、配給に頼るしかないまちなかと違って、田舎は食べるものがあるのがいい。秋が深まると落ちている栗や柿を拾っては食べた。
学校に通うようになったのは秋が深まってからだった。負傷した被爆者を収容していた飯室の国民学校が病院としての役目を終え、集落に分散していた教室から椅子と机をかついで山を越えて学校に向かった。授業らしい授業はなかった。先生たちも何を教えてよいのか分からず、半日くらいで下校になる。山越えの通学は片道1時間半。自分で編んだ草履は2日で駄目になった。舗装されていない山道は冬には滑って大変だった。
父・清次郎の傷はだんだん癒えてきて、秋には兄・清八が除隊になって戻ってきた。生活再建のためには仕事を見つけなくてはいけない。陸軍の糧秣支廠に配属されていた兄は軍の物資に詳しく、宇品や大竹、下松などに出向いて様子を探った。目を付けたのは巻き取りの厚紙。コールタールを塗れば屋根の防水シートが作れる。復興に役立てるという条件で払い下げてもらい、1946(昭和21)年の新年早々に両親と兄は三篠に戻っていった。焼け跡の防空壕を寝場所にして、焼け野原で工具を集めながら操業再開の準備を始めた。生き残った家族全員が住めるようにバラックを建てた。
飯室を離れたのは3月31日。三篠ではバラックがまだ完成しておらず、すきま風が身に染みた。早朝には「3番線、東京行き発車」と、2キロ以上も離れた広島駅のアナウンスが聞こえてきた。焼け残った煙突が立つさまを見ながら、この地で再び生きる日々が始まった。
まず直面したのは食糧難だった。飯室から米はもらえたが、8人が暮らす家族には十分な量ではない。戦争中と同じく、刻んだサツマイモの茎やアカザなどの雑草を入れて雑炊の量を増やした。農家からカボチャなどの種をもらって蒔いたが、工場の廃材や屋根瓦が埋まる土地を耕すのは大変な作業だった。土を深く掘っては瓦礫を埋め、掘っては埋め。土地をかさ上げして水田を作り、足踏みの水車で水を引くと、くたくたになった。50坪ほどの田畑をつくり、豆やジャガイモ、野菜を育て、鶏やウサギも飼って自給自足の生活に追われた。
まだ配給制度が残り、軍の物資だったメリケン粉や乾パン、金平糖などが手に入ることもあった。メリケン粉のうどんは最高に美味だった。子どもたちが食べ終わるのを待って残りを食べていた母の姿に胸が痛んだ。横川駅や広島駅には闇市が立ち、ぬかや雑草などを混ぜ込んだ江波だんごもよく買った。うまくはなかったが、1人幾つまで、と買える数が決まっていた。
古巣の大芝国民学校の6年生に復帰した。校舎は焼けずに残っていたが、原爆で屋根が抜けて窓ガラスもなく、教室から見上げると青空が見えた。まともな授業はなかった。子どもたちは家の手伝いで忙しく、食べるものもないから昼前には下校。まずは教科書の墨塗りから始まり、これはどういうことかと頭が混乱したが、そのうちに慣れてしまった。教育の方針が定まらないから、先生も困っていたのだろう。戦時中の先生が残っていて、軍隊式の教育だったのが命令口調もなくなり、勉強らしいことはせぬまま。卒業写真も撮った記憶がない。
学制改革で新制中学ができた1947(昭和22)年春、広島市の第五中学校に入学した。自前の校舎はなく、鉄筋コンクリートだったため焼け残った袋町小学校の3階を間借りした。壁は抜けて床もガタガタ。荒天の日には雨が吹き込んだ。制服もなければ教科書すらない。椅子は生徒が作り、画板が机代わりだった。疎開から戻ってきたり海外から引き揚げてきたり、日に日に生徒の数が増えた。男の先生が3人いた。詰め襟姿の新卒の先生は「簿記とはBOOK KEEPINGという」と言い出すから驚いた。その先生の授業は1回で終わった。旧制の広島一中(現・広島国泰寺高校)から来たという化学の先生はいきなり原子量と分子量の授業を始め、水の分子量を計算せえ、と宿題を出すから困った。小学4年くらいからまともに授業を受けたことがないのだから。その一方で勉強することにも飢えていた。友人と本通りの本屋を巡り、金正堂に長居しすぎて店員に怒られたら次は廣文館へ、また怒られたら次へ。何とか答えを引き出した。
7月ごろには英語の教科書が届いたが、生徒全員分がそろわず、やむを得ず友人に1日借りて1冊を丸ごとノートに筆写した。そうすると、分からないなりにも法則のようなものが見え、英語のイメージができてきた。蘭学事始を学んだ昔の人はこんな調子だったんだろうか。戦後の欠乏状態の中での学びは、自分で勉強して答えを出す―すなわち自立の教育。身についた習慣はその後の人生でも大いに役立った。

袋町小学校に間借りしていた第五中学校時代。
前から2列目の左端が久永洪さん
起死回生
袋町の第五中への通学は短い期間だった。生徒数は増えるばかりで、学校を三つに分けて今の幟町中学校と国泰寺中学校、中広中学校が誕生した。2年生だった1948(昭和23)年から、幟町にできた真新しい校舎に通うことになった。三篠橋を渡って白島を抜けていくと、町工場の多い三篠と裕福な家が多かった幟町の違いを感じた。住宅難に対処しようと、陸軍用地だった基町には平屋の家がたくさん造られた。後に高層の公営住宅が建つ一帯だ。
英語がこれからは必要だろう。そう考えていた頃、ブラジル帰りの友人から、流川教会で英語を教えてくれると聞いて3カ月くらい通ってみた。友人は水のことをワラー、ワラー、と発音していた。
ジープに乗った進駐軍の憲兵隊(MP)に話しかけられたのは、江波だんごを買いに行ったときだった。「この辺でカトリック教会を知らないか」と尋ねてきた。日本語ができる兵士だった。知っている、と返事をしたらジープに乗せられ、「案内しろ」と。宗教的なものがバックにあるのか、進駐軍は教会を探して物資を運び入れたいんだろう。このときに初めてチョコレートをもらった。将校の帽子をかぶった兵士が、煙草を吸うため革靴の底でマッチを擦ったのに驚いた。靴底でこすっただけで火がつくんだから、こりゃ戦争も負けるのう、と思った。
1950(昭和25)年春に中学校を卒業し、新制高校の市立基町高校を受験したが、思い直して中高一貫の私立進学校・修道高校に入った。家業はまだ火の車だったが、修道の同級生には金持ちがたくさんいた。
家業では、屋根の防水シートをつくる仕事は半年たった1946(昭和21)年秋には終わっていた。材料の厚紙がなくなってしまった。さて次はどうするか、と父・清次郎と兄・清八は思案し、資材に詳しいブローカーから、ガソリンの代用品だった松根油が残っていて、塗料を作れると聞いた。兄は調査と研究を重ね、木に塗ると防水と防腐の効果があるとわかった。それで木造船の船底塗料を作ることになり、吉島の刑務所近くに工場を建てた。兄を社長にして会社も興し、宇品や木江、尾道、下松なんかの港町へ売りに歩いた。この頃には家業は技術者を雇っているから、家の手伝いというと農作業だった。

高校2年時の久永洪さん。社員に囲まれて

1954(昭和29)年に大阪で開催された
国際輸出見本市に出展

1956(昭和31)年作成
ロングロング見本帳表紙と内容
塗料は順調に売れ、生活も良くなってきたが、そのうちに大手の塗料会社が復活してくる。いつ金紙作りを再開するか。父の頭にあったのはそれだ。1950(昭和25)年には30坪の工場を建て、翌年には一時帰郷した三篠出身の日系2世から「アメリカでは家庭でたくさんの壁紙を貼っている。金紙も売れると思う」と聞きつけ、父は見本作りを始めた。しかし原材料や道具はまだ良質なものがそろわず、苦心して作った金紙も「破れやすい」と不評だった。金箔の代わりに金粉を紙にスプレー方式で吹きつけて作ることを考案し、休日返上で製造して「平和金」と名付けて売り出した。しばらくすると苦情が寄せられた。折り曲げると金粉がはがれてしまう、というのだ。失敗作だった。
このピンチを救ったのは二つの家族(夫同士が兄弟=弟は被爆死=、妻同士が姉妹)で、子どもを含む全員が一致団結して一日も早い成功を祈りつつ金紙作りの仕事をし、合間に自給自足のために農作業をする生活だった。
やはり本来の金箔や銀箔を使った良質な商品を作るしかない。その頃には朝鮮戦争の特需もあって国内の復興が加速していた。東京の問屋と相談して見本帳を作ってみたが、売れる相手はお寺くらいで、これでは商売にならない。
1953(昭和28)年、塗料は潮時と考えていた兄は金紙製造に復帰した。父はもんもんとしながら金紙を作っていたが、そのうちに金策が厳しくなってくる。県庁や市役所に出入りしていた兄は、国内が駄目なら国外へ、ということで、中小企業の物品を紹介する国際輸出見本市の話に乗った。翌年に大阪で見本市が開催され、広島県のブースに出展した。会場を訪れたアメリカのバイヤーから、美術館や博物館にある古い金屏風みたいな金紙ができないか、と聞かれた。それをヒントに、箔と箔の境目を工夫し、縦と横の線でアクセントを出して古美を感じさせる商品を作ってみたら、これがアメリカで爆発的にヒットした。「久永」の意味は長い長い。「ロングロング」と名付けた起死回生の製品は、断ち切られかけた家業を救い、広島の金紙製造の伝統も救うことになった。

会社を継いで
まだ家業が苦境にあったさなかに大学受験の時期を迎えた。京大を受けたが不合格で、家業の手伝いを1年して1954(昭和29)年春、広島大学工学部の工業化学科に入学した。しかし家業はまだ落ち着かず、半年通って休学した。1年後に復帰する際には元の学科ではなく、工業経営学科に替えた。物作りに全身全霊を傾ける父・清次郎のことは尊敬していたが、戦後に入ってきた経営の新しい手法を学ばなければと思い立った。
とはいえ家業を継ぐことを決めていたわけではない。もはや戦後ではない、と言われた時期。大学の友人たちは有名企業を目指していた。家業は1954(昭和29)年に法人に改組して「広島瀝青社」となり、前年には80坪の工場も増築していた。兄・清八はしっかりと会社を支えていて、自分が家業に必要なのかという思いがあった。
その迷いを打ち消した出会いがあった。耐水性の色紙を作っている大阪の会社に教えを請いに行ったとき、先方の社長は若い頃に金紙を作ろうとして何度も失敗した体験談を話してくれた。あんた方の会社の技術はたいしたもんだよ―。その言葉に自らの不明を恥じた。また、大阪・新歌舞伎座の建設工事で金箔貼の依頼があり、そこで建築家の村野藤吾氏の設計による金銀装飾のまばゆい世界を目の当たりにして心は決まった。大学を卒業すると家業の会社に入社し、販売、企画、経営を担当する兄を製造と技術開発の分野から支えた。
戦後復興から高度成長へと加速する時代、高品質の商品で販路を国内外に拡大し、高級ホテルや有名な神社仏閣、美術館、空港のVIPルーム、公共施設などの仕事を次々と手がけた。会社は1962(昭和37)年に「広島歴清社」に改称し(後に「歴清社」)、兄が社長に就任した。1981(昭和56)年12月、貿易振興への貢献で前月に紫綬褒章を受章したばかりだった兄が58歳の若さで急逝した。後を継いで4代目の社長に就き、初代・清次郎による創業から100年となった2005(平成17)年まで勤め上げた。伝統と革新を胸に新商品の開発に果敢に挑み、そのための機械の開発や器具の調整は全て自前。人生で培ってきた自立心がその根底にあった。
社長在任中の忘れられない出来事の一つが、1990(平成2)年に訪問したニューヨークの国連本部。中に入ると直径30センチほどの柱が20本くらい並び、貼られた金箔は古びていながらも優しい光を放っていた。本会議場に入ると、光り輝く金色の大きな壁面に、国連の紋章が見えた。人類が古くから大切にしてきた金は、ただの色ではない。癒やしと希望を感じさせる力がある。そこには愛と平和がある―。それはすなわち、ヒロシマが求め続ける世界恒久平和に通じるものだった。

◀︎作業に励む若き日の久永洪さん
まばゆい金の輝きに包まれる国連本部の本会議場 UN Photo/Manuel Elias
会社を継いで

まばゆい金の輝きに包まれる国連本部の本会議場 UN Photo/Manuel Elias
まだ家業が苦境にあったさなかに大学受験の時期を迎えた。京大を受けたが不合格で、家業の手伝いを1年して1954(昭和29)年春、広島大学工学部の工業化学科に入学した。しかし家業はまだ落ち着かず、半年通って休学した。1年後に復帰する際には元の学科ではなく、工業経営学科に替えた。物作りに全身全霊を傾ける父・清次郎のことは尊敬していたが、戦後に入ってきた経営の新しい手法を学ばなければと思い立った。
とはいえ家業を継ぐことを決めていたわけではない。もはや戦後ではない、と言われた時期。大学の友人たちは有名企業を目指していた。家業は1954(昭和29)年に法人に改組して「広島瀝青社」となり、前年には80坪の工場も増築していた。兄・清八はしっかりと会社を支えていて、自分が家業に必要なのかという思いがあった。
その迷いを打ち消した出会いがあった。耐水性の色紙を作っている大阪の会社に教えを請いに行ったとき、先方の社長は若い頃に金紙を作ろうとして何度も失敗した体験談を話してくれた。あんた方の会社の技術はたいしたもんだよ―。その言葉に自らの不明を恥じた。また、大阪・新歌舞伎座の建設工事で金箔貼の依頼があり、そこで建築家の村野藤吾氏の設計による金銀装飾のまばゆい世界を目の当たりにして心は決まった。大学を卒業すると家業の会社に入社し、販売、企画、経営を担当する兄を製造と技術開発の分野から支えた。
戦後復興から高度成長へと加速する時代、高品質の商品で販路を国内外に拡大し、高級ホテルや有名な神社仏閣、美術館、空港のVIPルーム、公共施設などの仕事を次々と手がけた。会社は1962(昭和37)年に「広島歴清社」に改称し(後に「歴清社」)、兄が社長に就任した。1981(昭和56)年12月、貿易振興への貢献で前月に紫綬褒章を受章したばかりだった兄が58歳の若さで急逝した。後を継いで4代目の社長に就き、初代・清次郎による創業から100年となった2005(平成17)年まで勤め上げた。伝統と革新を胸に新商品の開発に果敢に挑み、そのための機械の開発や器具の調整は全て自前。人生で培ってきた自立心がその根底にあった。
社長在任中の忘れられない出来事の一つが、1990(平成2)年に訪問したニューヨークの国連本部。中に入ると直径30センチほどの柱が20本くらい並び、貼られた金箔は古びていながらも優しい光を放っていた。本会議場に入ると、光り輝く金色の大きな壁面に、国連の紋章が見えた。人類が古くから大切にしてきた金は、ただの色ではない。癒やしと希望を感じさせる力がある。そこには愛と平和がある―。それはすなわち、ヒロシマが求め続ける世界恒久平和に通じるものだった。

▲作業に励む若き日の久永洪さん


陸軍被服支廠から受注生産した軍服などの包装紙。その製造のために自前で機械を造り、煙突も建てた。それらに宿るのは戦争の記憶。いま、ロングロングが放つ金色の光が、ヒロシマの復興とともに歩んだ久永洪さんの人生を照らす。

タテ・ヨコ方向にしわを入れて
伸縮自在になる被服支廠の包装紙

包装紙を作るために自作した機械

ロングロングの製作を始めた初期の風景


陸軍被服支廠から受注生産した軍服などの包装紙。その製造のために自前で機械を造り、煙突も建てた。それらに宿るのは戦争の記憶。いま、ロングロングが放つ金色の光が、ヒロシマの復興とともに歩んだ久永洪さんの人生を照らす。

タテ・ヨコ方向にしわを入れて
伸縮自在になる被服支廠の包装紙

包装紙を作るために自作した機械

ロングロングの製作を始めた初期の風景
未来への財産
時代の激変を経ても生き残ったのは金紙が持つ力だった。
大型施設の内装から住宅のインテリア、さまざまなアーティストの素材。製造過程で生まれる端材すらも商品に替え、コーヒーや黒豆に加えれば黒の輝きをいっそう引き立てる。100年企業はさまざまな製品を創り出すことで文化の裾野を広げてきた。
文化を創ることは一気にできることではない。仕事の依頼があれば絶対に断らず「どうすれば要求に応えられるか」を考え、それが人材や技術、デザイン力などの経験値を高め、品質を向上させていく。そうすることで「自分たちにしかできないこと」を生み出し、オンリーワン企業として歩んできた。
進取の精神を具現化しつつも大切に守ってきたのは、核兵器による惨禍という人類史上初の苦難を経験し、広島の人々と復興を歩んできたというアイデンティティーだ。爆風と火炎に耐えた円柱形の煙突は工場の換気用にいまも使われ、焼け残った倉庫も現役で、広島市の被爆建物リストに登録されている。煙突と倉庫を囲むように建てられた工場は1959(昭和34)年、祇園町(当時、現・広島市安佐南区)の小学校から廃材を引き取って作った。あの夏、一家が北に向かって逃れていった道すがらにあった小学校の体育館や階段の部材だ。会社のショールームに入る際、玄関先で目に入る御影石は、かつては大灯籠の台座だった。
財産はオンリーワンの技術だけではない。原爆に耐えて生き抜いてきた記憶を未来に残していくことも大きな使命になっている。
あの焼け野原から、よくここまで復興したなあ―。
その感慨には、自らの人生と、家族が流した汗と涙、そしてヒロシマが歩んだ歳月がこもっている。

-
歴清社
Rekiseisha
広島が誇るオンリーワン企業。日本の伝統工芸技術である箔押しを用いた金紙製造の匠で世界に名をはせ、2025(令和7)年で創業120年になる。
まるで本物の金箔のように、長く使っても変色することなく、かつ実用性にも優れた金紙。神社仏閣、皇室、カルティエやティファニーなどのブランドショップ、国内外の高級ホテル、東京スカイツリー、GINZASIX(ギンザシックス)、アカデミー賞会場や映画のセット―内装を彩る金の輝きそれを国内で初めて製品化した歴清社の歴史は、1905(明治38)年に創業した「久永清次郎商店」にさかのぼる。
初代・久永清次郎の生家は浅野城下で刀剣商を長年営んできた。商いの転換を余儀なくされたのが、明治維新に伴い1876(明治9)年に発令された廃刀令だった。出入りをしていた武家屋敷の調度品に着目し、金銀屏風の売買を始めたが、京都から仕入れる本金や本銀の屏風は高価だった。そこで真鍮製でも色が変わらず、実用にも耐えられる金紙を作ることに挑み、接着剤などに試行錯誤しながら技術開発に成功した。
1925(大正14)年に「洋箔押紙製造方法」で特許認証を得て、1928(昭和3)年には創業の地・堀川町(現・広島市中区)から三篠本町(現・広島市西区)に移転した。戦時統制の影響を受けて1943(昭和18)年に金紙の製造を中止し、戦時中は陸軍広島被服支廠で製造される軍服の包装紙を手がける。
1945(昭和20)年8月6日の原爆投下による工場焼失で操業の中断を余儀なくされるが、戦後は屋根用防水紙などの製造で事業を再開した。さらに輸出用の金紙製造に注力し、壁紙「ロングロング」シリーズのヒットにより海外市場に進出。1954(昭和29)年に有限会社「広島瀝青社」を設立し、1962(昭和37)年に「広島歴清社」に改称、1979(昭和54)年に株式会社「歴清社」になる。
歴清社は発展と苦難の記憶を刻んだ地で操業を続け、日本の美意識を象徴する箔文化を継承しながら、現代的な創造性で世界を魅了している。
1935(昭和10)年に完成した5階建ての工場

1935(昭和10)年に完成した5階建ての工場



従業員たちが黙々と手を動かして
金箔を貼っていく。
丁寧な作業がオンリーワンの製品を生み出す
提供 朝日新聞社 2005(平成17)年撮影

1925(大正14)年に
取得した特許証が、
広島の金紙製造の礎となった

1925(大正14)年に
取得した特許証が、
広島の金紙製造の礎となった

被爆したショールーム前の大灯籠の台座
◀︎従業員たちが黙々と手を動かして
金箔を貼っていく。
丁寧な作業がオンリーワンの製品を生み出す
提供 朝日新聞社 2005(平成17)年撮影